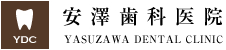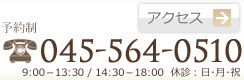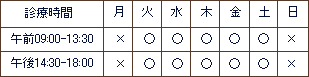図1:重度な開咬
図1~図3まで、臼歯部(奥歯)しか接触していない重度な開咬から犬歯の部分が接触していない軽度な開咬(隠れ開咬)まで、その状態はさまざまです。
前回のコラム「オーガニック・オクルージョン(Organic Occlusion)」で、前歯にはあごを動かす時、顎を誘導する役割があるとお話をしました。
しかし、この開咬(Open Bite)の方の場合、上下の前歯は全く接触していないため、顎をうまく誘導することができません。
そのため、臼歯(奥歯)に相当な力の負担がかかってしまうのです。
ですから、このような噛みあわせの方は、歯のトラブルが非常に多いのです。
つめもの・かぶせものが外れやすかったり、歯の根の病気になりやすかったり、
歯周病になるリスクも非常に高いのです。

図2:顎偏位を伴った中程度の開咬
そして歯のトラブルばかりではなく、その他の口腔の機能にさまざまな影響を及ぼします。
ひとつには咀嚼の問題です。上下の前歯が噛みあっていませんので、前歯で噛み切ることが難しく、あまり噛まずに飲み込んでしまうのです。
そして、二つ目には発音の問題です。どうしても息が漏れやすく舌足らずな発音になってしまいます。
さらに、三つ目には口呼吸の問題です。本来、呼吸は鼻を使ってするものですが、前歯が開いた状態になっていると、お口を閉じることが難しく、口呼吸をしてしまうのです。つねにその状況になりますと、お口が乾燥しますので、虫歯になりやすい環境になります。
また口呼吸は免疫低下の原因といわれていますので、全身の健康のことを考えても、口呼吸しないようにしなければなりません。
その治療法ですが、かみ合わせの改善はいうまでもありませんが、同時にお口の周りの筋肉が弱い方などは、口腔筋機能訓練(MFT)も併用して治療が必要となるでしょう。

図3:軽度な開咬「隠れ開咬」
開咬(Open Bite)の問題点
- かぶせものや詰め物が外れやすい
- 歯の根の病気になりやすい
- 歯が破折しやすい
- 虫歯になりやすい
- 歯周病になるリスクが非常に高い
- あごの筋肉や関節に負担になりやすいため、顎関節症を引き起こす可能性が高い
- 咀嚼障害
- 発音障害
- 口呼吸による免疫低下